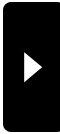2024年10月30日
2024衆院選を踏まえて予想される首相指名の行方
昨年度は中学社会科で公民的分野の指導をしておりましたが、衆議院議員総選挙後に必ず開かれる国会、それが「特別会」です。
特別国会とも称されておりますが、絶対行わなくてはならないことが「内閣総理大臣の指名」です。
衆議院は任期4年ながらも、解散されることがあるため、同じく任期6年で解散がない参議院よりも民意を反映しやすいと考えられており、特別会では最初に内閣総理大臣を決めるところから議論が始まります。
というわけで、今回の選挙では与野党ともに簡単に過半数を確保できない結果に至りましたので、各種報道でもいろんな話が出ています。
自公連立+野党、同一本釣り、非自民連立などですが、国民民主党の玉木代表が「決選投票でも自身に入れる」という話をしているところから、私は「自公連立継続による少数与党政権の継続」になるとみます。
1回目の投票で過半数を占めればよいのですが、そうならないことは先に記したとおりです。
でもって、次の決選投票で上位2名のどちらかに票を入れることになるわけですが、与党系が221議席、野党系が244議席で、国民民主党28議席が「無効票」となれば、221対216となって、少数与党になるものの石破総理の続投が決まります。
決選投票では、票数が多い方が指名を受けることになりますので、必ずしも出席議員の過半数の票でなくてもよいのです。
参議院では、自公で過半数の議席を有していますので、仮に自公が関わらない連立政権を作るにしても、参議院で法案可決は困難となります。
野党が政権奪取するには、参議院でキャスティングボードを握る公明党を取り込めるか、左派政党を巻き込むのかどうかといった方針を決めて臨まないと、困難な道のりが待ち構えています。
幸い、来年夏に参議院通常選挙が行われますので、現状を考えますと、少数与党で自公連立を来夏まで継続させ、通常選挙の結果を受けて、次のステージに進むのが賢い気がします。
その間で懸案の政治改革を野党を巻き込んで成立させて、おカネのかからない、透明な政治活動への転換、国民生活を意識した経済対策といった案件を処理していけるかで、また国民は適切な判断を下すことでしょう。
これが滞ることになれば参議院通常選挙で敗北する政党も出てくるでしょうから、どの党も真摯に政治活動に取り組むでしょうし、国民も降って湧いた無計画な増税論にも反対票で阻止することができます。
中庸というのが、政治においては一番国民にとって不利益を被りにくい状況のように思います。
特別国会とも称されておりますが、絶対行わなくてはならないことが「内閣総理大臣の指名」です。
衆議院は任期4年ながらも、解散されることがあるため、同じく任期6年で解散がない参議院よりも民意を反映しやすいと考えられており、特別会では最初に内閣総理大臣を決めるところから議論が始まります。
というわけで、今回の選挙では与野党ともに簡単に過半数を確保できない結果に至りましたので、各種報道でもいろんな話が出ています。
自公連立+野党、同一本釣り、非自民連立などですが、国民民主党の玉木代表が「決選投票でも自身に入れる」という話をしているところから、私は「自公連立継続による少数与党政権の継続」になるとみます。
1回目の投票で過半数を占めればよいのですが、そうならないことは先に記したとおりです。
でもって、次の決選投票で上位2名のどちらかに票を入れることになるわけですが、与党系が221議席、野党系が244議席で、国民民主党28議席が「無効票」となれば、221対216となって、少数与党になるものの石破総理の続投が決まります。
決選投票では、票数が多い方が指名を受けることになりますので、必ずしも出席議員の過半数の票でなくてもよいのです。
参議院では、自公で過半数の議席を有していますので、仮に自公が関わらない連立政権を作るにしても、参議院で法案可決は困難となります。
野党が政権奪取するには、参議院でキャスティングボードを握る公明党を取り込めるか、左派政党を巻き込むのかどうかといった方針を決めて臨まないと、困難な道のりが待ち構えています。
幸い、来年夏に参議院通常選挙が行われますので、現状を考えますと、少数与党で自公連立を来夏まで継続させ、通常選挙の結果を受けて、次のステージに進むのが賢い気がします。
その間で懸案の政治改革を野党を巻き込んで成立させて、おカネのかからない、透明な政治活動への転換、国民生活を意識した経済対策といった案件を処理していけるかで、また国民は適切な判断を下すことでしょう。
これが滞ることになれば参議院通常選挙で敗北する政党も出てくるでしょうから、どの党も真摯に政治活動に取り組むでしょうし、国民も降って湧いた無計画な増税論にも反対票で阻止することができます。
中庸というのが、政治においては一番国民にとって不利益を被りにくい状況のように思います。
2024年05月05日
しれっと県民共済が手術共済金の改悪をしてた件
今日はお見合いに出かけ、眼鏡屋で昨年購入した眼鏡の見え方について確認をし、併せて眼鏡のクリーニング&住所変更を済ませ、家で引っ越し荷物の整理をしていました。
だいぶ段ボールも整理され、不用品もあぶり出されてきたところで、ふと先月届いていて未開封の郵便物が見つかりました。
県民共済の加入証書で、年度更新による新年度の保障内容の内容が記されていましたが、平成31年4月に尿路結石で入院しており、その時は手術費が26万円ほどで、一時的にATMから現金を下ろして立て替えてから、高額療養費制度を利用して医療費総額は6万円程度で済みました。
県民共済からの共済金は22万円ほどで、手術共済金が20万円と、大きかったです(※医療特約1型加入分)。
さて、封書の中を見てみると、「保障をアップデート」と、いいような感じで案内されています。
総合保障型では、入院共済金(病気)が事故と同額になっています(+500円/日・2型)。
他方、気になったのが「手術共済金」の区分がこれまで3区分だったのが4区分になったことです。
一応FP2級(個人資産)保有ですので、隅々までくまなく見ていくと、手術費が1.4万円相当未満で2万円の共済金が入る場合が新たにできる反面、従前の金額から確実に下がる、ということです。
【手術費】
1.4万円以上5万円未満:2024年3月までは5万円⇒2万円
5万円以上15万円未満:2024年3月までは10万円⇒5万円
15万円以上30万円未満:2024年3月までは20万円⇒10万円
※30万円以上は20万円のままで変化なし
尿路結石の手術費(26万円)が据え置きだとすると、2024年4月以降の手術共済金は10万円に半減します。
高額療養費制度を使っても、収入が往時より7割近く増えているため、8万円程度で2万円ほど負担増となり、手術金が3割負担前提でほぼ同額の補填にあてがわれる程度になる、ということです。
しかし、1.4万円未満の手術なんてものにわざわざ手術共済金がいるのかどうか、そもそも疑問です。
3割負担であれば、5千円もしません。
現在の勤務先では、いろんな団体が活動しており、その中で保険系の勧誘もあります。
今回の変更を機に、改めて条件を確認しておこうと思います。
だいぶ段ボールも整理され、不用品もあぶり出されてきたところで、ふと先月届いていて未開封の郵便物が見つかりました。
県民共済の加入証書で、年度更新による新年度の保障内容の内容が記されていましたが、平成31年4月に尿路結石で入院しており、その時は手術費が26万円ほどで、一時的にATMから現金を下ろして立て替えてから、高額療養費制度を利用して医療費総額は6万円程度で済みました。
県民共済からの共済金は22万円ほどで、手術共済金が20万円と、大きかったです(※医療特約1型加入分)。
さて、封書の中を見てみると、「保障をアップデート」と、いいような感じで案内されています。
総合保障型では、入院共済金(病気)が事故と同額になっています(+500円/日・2型)。
他方、気になったのが「手術共済金」の区分がこれまで3区分だったのが4区分になったことです。
一応FP2級(個人資産)保有ですので、隅々までくまなく見ていくと、手術費が1.4万円相当未満で2万円の共済金が入る場合が新たにできる反面、従前の金額から確実に下がる、ということです。
【手術費】
1.4万円以上5万円未満:2024年3月までは5万円⇒2万円
5万円以上15万円未満:2024年3月までは10万円⇒5万円
15万円以上30万円未満:2024年3月までは20万円⇒10万円
※30万円以上は20万円のままで変化なし
尿路結石の手術費(26万円)が据え置きだとすると、2024年4月以降の手術共済金は10万円に半減します。
高額療養費制度を使っても、収入が往時より7割近く増えているため、8万円程度で2万円ほど負担増となり、手術金が3割負担前提でほぼ同額の補填にあてがわれる程度になる、ということです。
しかし、1.4万円未満の手術なんてものにわざわざ手術共済金がいるのかどうか、そもそも疑問です。
3割負担であれば、5千円もしません。
現在の勤務先では、いろんな団体が活動しており、その中で保険系の勧誘もあります。
今回の変更を機に、改めて条件を確認しておこうと思います。
2023年08月18日
最低賃金が897円に上がって起こること
本ブログが謎のランキング11位に入ったタイミングでこの記事を書いています。
早ければ(異議申し立て等があると遅れるため)10月6日より南九州2県の最低賃金が897円となることが決まりました。
九州では福岡県が941円、佐賀県が900円、大分県が899円、長崎県と熊本県が898円ですので、北の方が高い状況になりますが、私がアルバイトを始めた1998年の最低賃金は579円でした。
54.9%増えたのは素直にうれしいものですが、あの時代の安月給15万円の日給が6,000円でした(15万÷25日)。
8時間労働で時給換算ですと750円になりますから、897円になると、最低日給(8時間の場合)は7,176円になります。
最低賃金の上昇は、日給の底上げにもつながります。
ただ、基本給の上昇とは必ずしもイコールではありません。
以前勤務していたブ○ック企業では、基本給が15万円で、それに役職・成果報酬手当と時間外労働手当(いわゆる見込み残業代)が上乗せされて2x万円でした。
時間外労働手当を除く支給額が最低賃金を上回っていれば違法にはなりませんので、辞めた時の退職金が22.5万円(基本給×1.5、勤続年数無視)で絶句でした。
ゆえにブ○ック企業呼ばわりしている次第ですが。
ハローワークでこの企業の求人を見てみると、今は総支給が28万円に上がっています。
私はこの額未満で課長職に就いていた次第で、なかなかひどい扱いですね、教員になって良かったと率直に思います。
18時半出勤、翌4時退勤なんて日程もありましたから、宿泊体験学習・修学旅行の引率以外で夜勤が無いのは良いものです。
低賃金の企業から高賃金の仕事への移動も増えてくるでしょうし、生徒たちが将来アルバイトする時にも同じ仕事でより多く稼げることにつながり、稼ぐ楽しみが見つかると将来の展望も変わってくることでしょう。
来年は900円台も視野に入ってきますし、仮に1,000円になると最低日給(8時間の場合)も8,000円になります。
まだまだ乖離がありますし、「同一労働同一賃金」の実現には程遠い面もあります。
何はともあれ、人手不足が続くうちはこの傾向が変わることはありませんので、経済状況の推移に注目です。
早ければ(異議申し立て等があると遅れるため)10月6日より南九州2県の最低賃金が897円となることが決まりました。
九州では福岡県が941円、佐賀県が900円、大分県が899円、長崎県と熊本県が898円ですので、北の方が高い状況になりますが、私がアルバイトを始めた1998年の最低賃金は579円でした。
54.9%増えたのは素直にうれしいものですが、あの時代の安月給15万円の日給が6,000円でした(15万÷25日)。
8時間労働で時給換算ですと750円になりますから、897円になると、最低日給(8時間の場合)は7,176円になります。
最低賃金の上昇は、日給の底上げにもつながります。
ただ、基本給の上昇とは必ずしもイコールではありません。
以前勤務していたブ○ック企業では、基本給が15万円で、それに役職・成果報酬手当と時間外労働手当(いわゆる見込み残業代)が上乗せされて2x万円でした。
時間外労働手当を除く支給額が最低賃金を上回っていれば違法にはなりませんので、辞めた時の退職金が22.5万円(基本給×1.5、勤続年数無視)で絶句でした。
ゆえにブ○ック企業呼ばわりしている次第ですが。
ハローワークでこの企業の求人を見てみると、今は総支給が28万円に上がっています。
私はこの額未満で課長職に就いていた次第で、なかなかひどい扱いですね、教員になって良かったと率直に思います。
18時半出勤、翌4時退勤なんて日程もありましたから、宿泊体験学習・修学旅行の引率以外で夜勤が無いのは良いものです。
低賃金の企業から高賃金の仕事への移動も増えてくるでしょうし、生徒たちが将来アルバイトする時にも同じ仕事でより多く稼げることにつながり、稼ぐ楽しみが見つかると将来の展望も変わってくることでしょう。
来年は900円台も視野に入ってきますし、仮に1,000円になると最低日給(8時間の場合)も8,000円になります。
まだまだ乖離がありますし、「同一労働同一賃金」の実現には程遠い面もあります。
何はともあれ、人手不足が続くうちはこの傾向が変わることはありませんので、経済状況の推移に注目です。
2022年02月24日
侵略国家を滅ぼす方法~第二次大戦の敗戦から学ぶ~
信長の野望、提督の決断、大戦略、Victoria等々、合戦・海戦・空中戦をゲームで楽しむこと30年、そんな私も二人の祖父がいずれも日中戦争の中国戦線に召集され、派兵された経験がありました。
母方の祖父は左腕が砲弾の影響で吹き飛んでない姿に、父方の祖父には戦争体験を聞いたところ、思い出したくもない感じで無言になった姿を間近に見て育っており、私個人は侵略戦争に大反対の立場です。
核大国が核の使用を示唆して威嚇し、侵攻するなど、どっかの国の将軍様のような有様に、国の威信も何もあったもんじゃないと思いつつ、特殊部隊がいるなら首謀者を誅殺すべきであろうと思っているところですが、国家テロの最たるものです。
さて、先の大戦では、資源が乏しいことと、海上輸送が滞り、物量に勝る連合国軍に押されて敗戦したわけですが、中国戦線では膠着状態のままでした。
枢軸国との三国同盟を結び、南部仏印進駐が決定打となって資源が入手しにくくなってしまい、太平洋に戦端が開かれてしまったことは残念ながらも、そもそも対華21ヶ条要求なんてものを中華民国に突き出し、中国東北地方の軍閥を爆殺して植民地確保に突っ走ったことが誤りでした。
奇しくも、民族自決がうたわれた国際連盟が立ち上がり、軍縮が行われる時流の変化が理解できずに他国を攻めることがどれだけ無意味なのか、昭和の初め頃の様子と今が何かリンクして見えてきます。
国際連合と訳されるUNは、そもそも連合国を指し、集団安全保障体制を意味します。
その加盟国同士が戦争となった以上は、当然抑止し、即時停戦を実現しなければなりません。
そのために、安全保障理事会の常任理事国には強い権限が与えられているわけですが、残念ながら常任理事国が戦を仕掛ける事態が起こってしまいました。
かつて東欧で民主化運動が起きた際は、「プラハの春」を代表に、ソ連軍が鎮圧に動きましたが、この場合は衛星国政権の要請の形であり、一方的な侵攻ではありませんでした。
アフガニスタンの場合も、共産主義政権でした。
今回は、完全なる独立主権国家への侵攻であり、これまでとは事情が違います。
まずは、国連の緊急総会を開き、常任理事国から侵略国を外すことです。
そうしなければ、抑止が働きません。
次に、バルト海、黒海、ベーリング海・北太平洋・日本海で臨検を実施し、物流を止めることです。
物資が欠乏すれば、継戦能力が低下することは先の大戦で分かっていることです。
また、金融的なネットワークから切り離し、輸出入決済を困難にさせます。
インターネット網の切断もサイバー攻撃を防ぐのに有効です。
我が国の防衛戦力は、宣戦布告されるまで維持です。
シベリア出兵のような派兵は厳禁です。
手を出されたら開戦し、沿海州とサハリンを制圧します。
艦船類も機雷をオホーツク海に敷き、封鎖させます。
地上兵力の輸送にシベリア鉄道を使われるとノモンハン事件の時のように厄介ですので、アメリカ軍と共同で爆撃等行うのが上策でしょう。
第二次大戦は、ナチスドイツのポーランド侵攻に端を発し、英仏が宣戦布告したことで始まりました。
そのポーランドに攻め込んだもう1ヶ国がソ連でした。
フランスはナチスドイツに敗北し、イギリスは本土防衛を完遂し、日本の真珠湾攻撃でアメリカが参戦して流れが変わりましたが、ポーランドに攻め込んだソ連はおとがめなしで、逆に独ソ戦になってから連合国の色合いが強くなりました。
我が国は原爆が落とされた唯一の国ですが、それゆえに核戦争には反対の立場を鮮明にせねばなりません。
被爆国に核の脅しなど、復興し、戦前なら10年に1度は派兵していた好戦的な姿勢も全くない今の我が国には何の意味もありません。
経済的に締め上げ、戦争をさせなくするのが一番です。
それでも攻めてくることがあるなら、領土問題を一気に解決してしまえば良いのです。
約束を守らない国は罰を受ける覚悟を持つべきです。
民族自決を堅持する姿勢が問われています。
母方の祖父は左腕が砲弾の影響で吹き飛んでない姿に、父方の祖父には戦争体験を聞いたところ、思い出したくもない感じで無言になった姿を間近に見て育っており、私個人は侵略戦争に大反対の立場です。
核大国が核の使用を示唆して威嚇し、侵攻するなど、どっかの国の将軍様のような有様に、国の威信も何もあったもんじゃないと思いつつ、特殊部隊がいるなら首謀者を誅殺すべきであろうと思っているところですが、国家テロの最たるものです。
さて、先の大戦では、資源が乏しいことと、海上輸送が滞り、物量に勝る連合国軍に押されて敗戦したわけですが、中国戦線では膠着状態のままでした。
枢軸国との三国同盟を結び、南部仏印進駐が決定打となって資源が入手しにくくなってしまい、太平洋に戦端が開かれてしまったことは残念ながらも、そもそも対華21ヶ条要求なんてものを中華民国に突き出し、中国東北地方の軍閥を爆殺して植民地確保に突っ走ったことが誤りでした。
奇しくも、民族自決がうたわれた国際連盟が立ち上がり、軍縮が行われる時流の変化が理解できずに他国を攻めることがどれだけ無意味なのか、昭和の初め頃の様子と今が何かリンクして見えてきます。
国際連合と訳されるUNは、そもそも連合国を指し、集団安全保障体制を意味します。
その加盟国同士が戦争となった以上は、当然抑止し、即時停戦を実現しなければなりません。
そのために、安全保障理事会の常任理事国には強い権限が与えられているわけですが、残念ながら常任理事国が戦を仕掛ける事態が起こってしまいました。
かつて東欧で民主化運動が起きた際は、「プラハの春」を代表に、ソ連軍が鎮圧に動きましたが、この場合は衛星国政権の要請の形であり、一方的な侵攻ではありませんでした。
アフガニスタンの場合も、共産主義政権でした。
今回は、完全なる独立主権国家への侵攻であり、これまでとは事情が違います。
まずは、国連の緊急総会を開き、常任理事国から侵略国を外すことです。
そうしなければ、抑止が働きません。
次に、バルト海、黒海、ベーリング海・北太平洋・日本海で臨検を実施し、物流を止めることです。
物資が欠乏すれば、継戦能力が低下することは先の大戦で分かっていることです。
また、金融的なネットワークから切り離し、輸出入決済を困難にさせます。
インターネット網の切断もサイバー攻撃を防ぐのに有効です。
我が国の防衛戦力は、宣戦布告されるまで維持です。
シベリア出兵のような派兵は厳禁です。
手を出されたら開戦し、沿海州とサハリンを制圧します。
艦船類も機雷をオホーツク海に敷き、封鎖させます。
地上兵力の輸送にシベリア鉄道を使われるとノモンハン事件の時のように厄介ですので、アメリカ軍と共同で爆撃等行うのが上策でしょう。
第二次大戦は、ナチスドイツのポーランド侵攻に端を発し、英仏が宣戦布告したことで始まりました。
そのポーランドに攻め込んだもう1ヶ国がソ連でした。
フランスはナチスドイツに敗北し、イギリスは本土防衛を完遂し、日本の真珠湾攻撃でアメリカが参戦して流れが変わりましたが、ポーランドに攻め込んだソ連はおとがめなしで、逆に独ソ戦になってから連合国の色合いが強くなりました。
我が国は原爆が落とされた唯一の国ですが、それゆえに核戦争には反対の立場を鮮明にせねばなりません。
被爆国に核の脅しなど、復興し、戦前なら10年に1度は派兵していた好戦的な姿勢も全くない今の我が国には何の意味もありません。
経済的に締め上げ、戦争をさせなくするのが一番です。
それでも攻めてくることがあるなら、領土問題を一気に解決してしまえば良いのです。
約束を守らない国は罰を受ける覚悟を持つべきです。
民族自決を堅持する姿勢が問われています。
2019年09月13日
鹿児島県の新総合体育館建設地に求めること
鹿児島中央駅西口を候補地として検討が進められてきた新総合体育館。
県庁東側と実家近くの農業試験場跡地の2か所で再検討を進めているという報道がなされておりますが、どちらも一長一短です。
県庁東側はそもそもマンション建設計画によって、県庁からの桜島の眺望が阻害されるのを防ぐために購入したといういきさつがあり、面積は少々足りない感じです。
ゆえに、駐車場も県庁のものが主体になり、駐車料金も中央駅近隣とさほど変わらないことが見込まれます。
渋滞は鹿児島市西部と南部・谷山方面からの流入が増えることが見込まれ、こちらの方が激しくなる見込みです。
だったら中央駅西口の方がJRや公共交通機関の便がいいのでこちらがいいのではないかと私は思います。
他方、実家近くの農業試験場跡地は土地も広く、駐車場も1,000台程度の整備は可能です。
しかし、道路が貧弱です。
区画整理されてかつてのケンカ道路もすっかり過去の話になったとは言え、片側二車線道路ではなく、県道鹿児島加世田線と慈眼寺地区・清和地区方面を結ぶ道は渋滞しやすくなっており、交通量の増加は歩道橋建設も必要になるのではないかと考えるほどになるものと予想します。
使える公共交通機関はJR慈眼寺駅くらいで、バスはコミュニティバスしか走っておらず、とても貧弱です。
通学に7時過ぎの加世田から来る始発バスを使っても高校に10分遅刻して遅刻届を出したこともありましたが、いくら指宿スカイラインや駅に県庁東口より近いと言っても、あそこはやめた方がいいです。
周辺道路の渋滞が酷くなってしまうだけです。
あと、飲食店は主要道路沿いしか用途地域の問題で建てられませんので、弁当を持参せずにお昼を摂るのは大変になるでしょう。
鹿児島中央駅近隣は幹線道路がどれも2車線ですし、駅近ですからパークアンドライドで来る分には立地はいいのです。
飲食店も充実しています。
実家近くが毎週末サマーナイト花火大会級の混雑になるのは、私としては断固反対です。
賑やかな施設は賑やかな場所に建てるべき、これが私の意見です。
県庁東側と実家近くの農業試験場跡地の2か所で再検討を進めているという報道がなされておりますが、どちらも一長一短です。
県庁東側はそもそもマンション建設計画によって、県庁からの桜島の眺望が阻害されるのを防ぐために購入したといういきさつがあり、面積は少々足りない感じです。
ゆえに、駐車場も県庁のものが主体になり、駐車料金も中央駅近隣とさほど変わらないことが見込まれます。
渋滞は鹿児島市西部と南部・谷山方面からの流入が増えることが見込まれ、こちらの方が激しくなる見込みです。
だったら中央駅西口の方がJRや公共交通機関の便がいいのでこちらがいいのではないかと私は思います。
他方、実家近くの農業試験場跡地は土地も広く、駐車場も1,000台程度の整備は可能です。
しかし、道路が貧弱です。
区画整理されてかつてのケンカ道路もすっかり過去の話になったとは言え、片側二車線道路ではなく、県道鹿児島加世田線と慈眼寺地区・清和地区方面を結ぶ道は渋滞しやすくなっており、交通量の増加は歩道橋建設も必要になるのではないかと考えるほどになるものと予想します。
使える公共交通機関はJR慈眼寺駅くらいで、バスはコミュニティバスしか走っておらず、とても貧弱です。
通学に7時過ぎの加世田から来る始発バスを使っても高校に10分遅刻して遅刻届を出したこともありましたが、いくら指宿スカイラインや駅に県庁東口より近いと言っても、あそこはやめた方がいいです。
周辺道路の渋滞が酷くなってしまうだけです。
あと、飲食店は主要道路沿いしか用途地域の問題で建てられませんので、弁当を持参せずにお昼を摂るのは大変になるでしょう。
鹿児島中央駅近隣は幹線道路がどれも2車線ですし、駅近ですからパークアンドライドで来る分には立地はいいのです。
飲食店も充実しています。
実家近くが毎週末サマーナイト花火大会級の混雑になるのは、私としては断固反対です。
賑やかな施設は賑やかな場所に建てるべき、これが私の意見です。
2017年12月26日
JR九州の2018年ダイヤ改正による減便に思う
大隅暮らしも5年目に入り、福岡の会社からヘッドハントの話も来てますが、今の勤務先の仕事が多忙につき、正月休みの間に落ち着いた環境の中で判断を下そうと考えているところです。
年間休日が40日近く増えるのはよいものの、不確定要素もまた多く、有休が取れること、契約社員6ヶ月からのスタートであること、昇給やインセンティブの中身といったことなどを吟味しないといけません。
齢40に近づくに連れて将来性という面も考慮しないといけなくなります。
北部九州へ移住となると、ツーリングで出かけられる範囲が拡大するため、その点では話に乗りたくなる気もするのですが、実際バイクに乗り続けるのか、というよりもひいきの店が見つかるのか、という方が問題です。
以上の次第で、移住する場合は手放すことになりそうですが、難しいところです。
さて、JR九州の2018年ダイヤ改正による減便が提起され、九州各県に波紋を投げかけているところです。
国鉄末期の特定地方交通線に指定される要件は、輸送密度4,000人/日に満たない路線とされ、ピーク時1時間に一方へ1,000人/時や、平均乗車キロが30kmを超え、輸送密度が1,000人/日以上であれば除外といった例外もあり、吉都線や日南線、肥薩線などは除外要件に該当してJR九州に引き継がれ、維持されています。
そうならなかったのが山野線や宮之城線、大隅線、志布志線の4線です。
1987~1988年までの間に廃線になりました。
おかげさまで、現在の最寄駅は西都城駅か国分駅、志布志駅という、不動産広告では徒歩500分台で案内される「鉄道不毛地区」住人となってしまっています。
さて、この30年の間で何が起きていたかと言えば、過疎化の進展です。
1987年の鹿児島県の人口は181万人。
2017年は、162万人です。
また、モータリゼーションを加速する高速道路網も整備され続け、1987年はえびのIC~鹿児島北ICにしか高速道路が通ってなかったのが、2017年は九州道全線と南九州道薩摩川内水引~鹿児島IC間、東九州道加治木JCT~鹿屋串良JCT間など各地を網羅しています。
今後の人口推移を見てみても、毎年1.6万人程度のペースで減少しており、徐々に減少幅が拡大傾向にあることから2027年には145万人を割る公算が大きいものと思われます。
そうした人口推移を踏まえてみれば、運転効率化による減便はやむを得ないというように受け取ることもできます。
しかしながら、鉄道が切り捨てられた地で4年余り生活してみると、奇妙なことに気づきます。
まず、鉄道に乗りません。
福岡や熊本に行こうと思い立って、用いる手段は自家用車です。
私は鉄道ファンなので、今年宗谷線稚内~旭川間、函館線旭川~滝川間、京急線の川崎~横浜間、相鉄線全線、小田急新百合ヶ丘~秦野間、京王線新宿~高幡不動間などに初乗車していますが、今年JR九州に乗ったのは現在霧島アートの森で個展を開催中の大学同期・あごぱん氏との酒飲みで、宿泊地の鹿児島中央駅から会場最寄りの慈眼寺駅間を往復したときのみとなっています。
鹿児島中央駅まで車やバスで2時間弱かかりますが、その時間を高速道路で走ると八代付近に出ます。
在来線は地域輸送に特化しているきらいがあり、スピードアップの努力もせず、路線改良の努力もせず、保線も指宿枕崎線の山川以西を見れば素人目でも明らかなように、草ぼうぼうです。
何が言いたいのかと言えば、非沿線地域の住民が鉄道に乗る理由を作れていないのです。
かつて急行えびのが肥薩線と吉都線を疾走していましたが、所要時間がかかり、九州道八代~えびの間が全通したことで高速バスとの競争にさらされることになり廃止となっています。
これ自体は仕方ないと思います。
ただ、鉄道に乗らない生活が長くなると、これが当たり前だと思って、余計に乗らなくなってしまうのです。
これがもう1つの奇妙な事実です。
解決策は、往時の特定地方交通線に該当する線区を維持する場合、上下分離を行った上で便数維持であるとか、土日祝日運行の長距離観光列車を走らせる、といったことになるでしょうか。
肥薩おれんじ鉄道に転換される前に旧鹿児島本線の薩摩大川駅~慈眼寺駅間を乗車した際、薩摩大川~川内間は1日7本程度しか普通列車の運行はありませんでした。
間に4時間空くこともあり、大変不便に感じていましたが、現在は往時の特急列車の本数とほぼ同じくらい列車が走っています。
おかげで、肥薩おれんじ鉄道友の会会員としてたまに旅程を立てて乗りに行きます。
儲からない区間で支援が得られないのであれば、バス転換も問題ないと思うところですが、その前に普段乗らない人を振り向かせるための努力が足りていたのか、JR九州には問いかけたいところです。
便利で早ければ間違いなく乗ります。
年間休日が40日近く増えるのはよいものの、不確定要素もまた多く、有休が取れること、契約社員6ヶ月からのスタートであること、昇給やインセンティブの中身といったことなどを吟味しないといけません。
齢40に近づくに連れて将来性という面も考慮しないといけなくなります。
北部九州へ移住となると、ツーリングで出かけられる範囲が拡大するため、その点では話に乗りたくなる気もするのですが、実際バイクに乗り続けるのか、というよりもひいきの店が見つかるのか、という方が問題です。
以上の次第で、移住する場合は手放すことになりそうですが、難しいところです。
さて、JR九州の2018年ダイヤ改正による減便が提起され、九州各県に波紋を投げかけているところです。
国鉄末期の特定地方交通線に指定される要件は、輸送密度4,000人/日に満たない路線とされ、ピーク時1時間に一方へ1,000人/時や、平均乗車キロが30kmを超え、輸送密度が1,000人/日以上であれば除外といった例外もあり、吉都線や日南線、肥薩線などは除外要件に該当してJR九州に引き継がれ、維持されています。
そうならなかったのが山野線や宮之城線、大隅線、志布志線の4線です。
1987~1988年までの間に廃線になりました。
おかげさまで、現在の最寄駅は西都城駅か国分駅、志布志駅という、不動産広告では徒歩500分台で案内される「鉄道不毛地区」住人となってしまっています。
さて、この30年の間で何が起きていたかと言えば、過疎化の進展です。
1987年の鹿児島県の人口は181万人。
2017年は、162万人です。
また、モータリゼーションを加速する高速道路網も整備され続け、1987年はえびのIC~鹿児島北ICにしか高速道路が通ってなかったのが、2017年は九州道全線と南九州道薩摩川内水引~鹿児島IC間、東九州道加治木JCT~鹿屋串良JCT間など各地を網羅しています。
今後の人口推移を見てみても、毎年1.6万人程度のペースで減少しており、徐々に減少幅が拡大傾向にあることから2027年には145万人を割る公算が大きいものと思われます。
そうした人口推移を踏まえてみれば、運転効率化による減便はやむを得ないというように受け取ることもできます。
しかしながら、鉄道が切り捨てられた地で4年余り生活してみると、奇妙なことに気づきます。
まず、鉄道に乗りません。
福岡や熊本に行こうと思い立って、用いる手段は自家用車です。
私は鉄道ファンなので、今年宗谷線稚内~旭川間、函館線旭川~滝川間、京急線の川崎~横浜間、相鉄線全線、小田急新百合ヶ丘~秦野間、京王線新宿~高幡不動間などに初乗車していますが、今年JR九州に乗ったのは現在霧島アートの森で個展を開催中の大学同期・あごぱん氏との酒飲みで、宿泊地の鹿児島中央駅から会場最寄りの慈眼寺駅間を往復したときのみとなっています。
鹿児島中央駅まで車やバスで2時間弱かかりますが、その時間を高速道路で走ると八代付近に出ます。
在来線は地域輸送に特化しているきらいがあり、スピードアップの努力もせず、路線改良の努力もせず、保線も指宿枕崎線の山川以西を見れば素人目でも明らかなように、草ぼうぼうです。
何が言いたいのかと言えば、非沿線地域の住民が鉄道に乗る理由を作れていないのです。
かつて急行えびのが肥薩線と吉都線を疾走していましたが、所要時間がかかり、九州道八代~えびの間が全通したことで高速バスとの競争にさらされることになり廃止となっています。
これ自体は仕方ないと思います。
ただ、鉄道に乗らない生活が長くなると、これが当たり前だと思って、余計に乗らなくなってしまうのです。
これがもう1つの奇妙な事実です。
解決策は、往時の特定地方交通線に該当する線区を維持する場合、上下分離を行った上で便数維持であるとか、土日祝日運行の長距離観光列車を走らせる、といったことになるでしょうか。
肥薩おれんじ鉄道に転換される前に旧鹿児島本線の薩摩大川駅~慈眼寺駅間を乗車した際、薩摩大川~川内間は1日7本程度しか普通列車の運行はありませんでした。
間に4時間空くこともあり、大変不便に感じていましたが、現在は往時の特急列車の本数とほぼ同じくらい列車が走っています。
おかげで、肥薩おれんじ鉄道友の会会員としてたまに旅程を立てて乗りに行きます。
儲からない区間で支援が得られないのであれば、バス転換も問題ないと思うところですが、その前に普段乗らない人を振り向かせるための努力が足りていたのか、JR九州には問いかけたいところです。
便利で早ければ間違いなく乗ります。
2016年09月15日
磯駅開設への動きに思うこと
毎晩MBCのローカルニュースをネットで見るのが日課なのですが、先ほど覗いてみたところ、仙巌園のアクセス駅として、磯地区への新駅設置の要望書を鹿児島市長に提出した、と出ていました。
私が在学中から月3回発行しているメルマガで確か触れていた気がしたため、探してみたら、昨年7月の第491号で磯新駅構想について意見を書いていましたので、以下転記します。
●【2015年7月12日発行分より】
今回は、世界遺産に「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」が隣国の妨害や干渉をはねのけて登録されましたが、旧集成館がある磯地域周辺は慢性的な渋滞が発生していることから、自分なりに思うところを記します。
国道10号磯バイパスは、いまだ山岳トンネル案で検討中のままなのですが、おりしもこの梅雨の大雨で鳥越トンネルと並行する市道が相次いで通行止めとなる事態を招いており、鹿児島市と姶良・霧島方面を結ぶ主要道である国道10号の改良は待ったなしの状況と言えます。
ただでさえ主要幹線道路であるというのに、仙巌園や世界遺産登録で注目を集めるであろう旧集成館がある磯地域への入り込み客は増加する可能性が高く、今の混雑に拍車がかかる懸念があります。
まあ、世界遺産に推薦された時点で、先手を打って仙巌園を運営する島津興業が要望した通り、磯地区に日豊線の新駅を作っておくべきだったかもしれません。
私が訪れた世界遺産のうち、海に面していて主要国道が1本走っているところとして、今年のGWでも訪れた広島県廿日市市の宮島口が挙げられます。
もともと宮島口駅があり、そこから国道の下を横断する地下道を通り、桟橋へ向かうわけですが、観光客が増えても道路交通に影響を減らす工夫がなされています。
磯駅を新設した場合、仙巌園からの桜島の眺望や近隣の景観対応を考えれば、仙巌園の真ん前に新駅を作るとしたら、ホームの上に屋根を開設することは難しく、市道と交差する踏切があることも手伝い、踏切の北側か南側のいずれかしか候補はありません。
さらに難しくしているのは、日豊線鹿児島駅~重富駅間13.9kmの間で電車を運行できるのが上下各1本に限られる、というものです。
日豊線は単線ですから、この区間で行き違いが出来るのは竜ヶ水駅だけです。
磯駅ができても行き違いはできませんので、減速による運行時間の増加と停車時間の増加によってこの区間の通過時間が増え、ダイヤ設定上の支障も出てくることになります。
以上の点を踏まえて、ダイヤの影響は無視して磯駅を新設するならば、踏切の南側(鹿児島駅より約1.8km地点)に新設します。
駅からは仙巌園方面へ地下通路を設け、国道10号を地下で通り抜けます。
ホーム数は、鹿児島駅側からのみの入れ込み線1を設けた2とすれば、通過列車にも対応でき、竜ヶ水駅方面へ向かわない増発分としても輸送量を確保できます。
指宿枕崎線の気動車を乗り入れれば指宿方面との連絡もよくなり、観光客の評判も良くなると考えます。
なお、トンネルを一部拡張して、トンネル内に分岐機を置かないと、4両編成停車はできなくなります。
宮島口の事例を基に対応するならば、JR新駅設置が望ましいというわけですが、ゆくゆくは磯バイパスを開通させ、宮崎の青島海岸のように、観光客と通過客の住み分けを図りたいものです。
以上がその内容ですが、1年ほど経った今読み返してみても、内容に違和感がなく、考え抜かれているものと我ながら感心します。
観光に当たって一番大事なのは、移動がしやすいことです。
行きたいときに気軽にすぐに出かけられること、これが大切です。
今日、JR九州の株式上場に伴う新規公開株の目論見書の回覧が始まったようです。
まだ仮条件なので上場額は未確定ですが、30万円少々になる見通しとのことです。
JR九州の鉄道事業は赤字なので、少しは改善に貢献できるかもしれません。
今後どうなるのか見守りたいところです。
私が在学中から月3回発行しているメルマガで確か触れていた気がしたため、探してみたら、昨年7月の第491号で磯新駅構想について意見を書いていましたので、以下転記します。
●【2015年7月12日発行分より】
今回は、世界遺産に「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」が隣国の妨害や干渉をはねのけて登録されましたが、旧集成館がある磯地域周辺は慢性的な渋滞が発生していることから、自分なりに思うところを記します。
国道10号磯バイパスは、いまだ山岳トンネル案で検討中のままなのですが、おりしもこの梅雨の大雨で鳥越トンネルと並行する市道が相次いで通行止めとなる事態を招いており、鹿児島市と姶良・霧島方面を結ぶ主要道である国道10号の改良は待ったなしの状況と言えます。
ただでさえ主要幹線道路であるというのに、仙巌園や世界遺産登録で注目を集めるであろう旧集成館がある磯地域への入り込み客は増加する可能性が高く、今の混雑に拍車がかかる懸念があります。
まあ、世界遺産に推薦された時点で、先手を打って仙巌園を運営する島津興業が要望した通り、磯地区に日豊線の新駅を作っておくべきだったかもしれません。
私が訪れた世界遺産のうち、海に面していて主要国道が1本走っているところとして、今年のGWでも訪れた広島県廿日市市の宮島口が挙げられます。
もともと宮島口駅があり、そこから国道の下を横断する地下道を通り、桟橋へ向かうわけですが、観光客が増えても道路交通に影響を減らす工夫がなされています。
磯駅を新設した場合、仙巌園からの桜島の眺望や近隣の景観対応を考えれば、仙巌園の真ん前に新駅を作るとしたら、ホームの上に屋根を開設することは難しく、市道と交差する踏切があることも手伝い、踏切の北側か南側のいずれかしか候補はありません。
さらに難しくしているのは、日豊線鹿児島駅~重富駅間13.9kmの間で電車を運行できるのが上下各1本に限られる、というものです。
日豊線は単線ですから、この区間で行き違いが出来るのは竜ヶ水駅だけです。
磯駅ができても行き違いはできませんので、減速による運行時間の増加と停車時間の増加によってこの区間の通過時間が増え、ダイヤ設定上の支障も出てくることになります。
以上の点を踏まえて、ダイヤの影響は無視して磯駅を新設するならば、踏切の南側(鹿児島駅より約1.8km地点)に新設します。
駅からは仙巌園方面へ地下通路を設け、国道10号を地下で通り抜けます。
ホーム数は、鹿児島駅側からのみの入れ込み線1を設けた2とすれば、通過列車にも対応でき、竜ヶ水駅方面へ向かわない増発分としても輸送量を確保できます。
指宿枕崎線の気動車を乗り入れれば指宿方面との連絡もよくなり、観光客の評判も良くなると考えます。
なお、トンネルを一部拡張して、トンネル内に分岐機を置かないと、4両編成停車はできなくなります。
宮島口の事例を基に対応するならば、JR新駅設置が望ましいというわけですが、ゆくゆくは磯バイパスを開通させ、宮崎の青島海岸のように、観光客と通過客の住み分けを図りたいものです。
以上がその内容ですが、1年ほど経った今読み返してみても、内容に違和感がなく、考え抜かれているものと我ながら感心します。
観光に当たって一番大事なのは、移動がしやすいことです。
行きたいときに気軽にすぐに出かけられること、これが大切です。
今日、JR九州の株式上場に伴う新規公開株の目論見書の回覧が始まったようです。
まだ仮条件なので上場額は未確定ですが、30万円少々になる見通しとのことです。
JR九州の鉄道事業は赤字なので、少しは改善に貢献できるかもしれません。
今後どうなるのか見守りたいところです。
2014年11月07日
鹿児島・肥後両銀行の経営統合報道の背景に見えるもの
ゆうちょ銀行以外では、一番長い付き合いの鹿児島銀行(以下鹿銀)とは、時にバイクローンを組む際にお世話になり、時にマイカーローンを組もうとした際は、社歴の短さで事前に蹴られるなど、恩仇ともにあるところですが、何はともあれ毎月の光熱水費&新聞代支払いにおけるメインバンクということもあり、お世話になっているところです。
さて、そんな鹿銀も、隣は熊本県の肥後銀行(以下肥後銀)と経営統合に向けて協議中という報道を聞き、驚いているところです。
鹿児島の経済圏からして、旧薩摩藩に属する都城市などを抱える宮崎の地方銀行との経営統合の方がすんなり飲み込めるところですが、よりによって熊本県の銀行というところが、今回の裏側を探る上で面白い所です。
まず、鹿銀・肥後銀とも、都市銀行の次の格に当たる地方銀行で、鹿児島・熊本両県の地域一番行といってよい存在です。
そして、両行の主力地域において、他県に本拠を置く銀行からの攻勢を受けています。
鹿児島では宮崎銀行、熊本ではふくおかフィナンシャルグループ傘下の熊本銀行です。
私が住む大隅は宮崎に近いこともあり、時折新聞広告を見るにつけ、宮崎銀行の攻撃的営業姿勢を広告から感じ取っています。
まあ、心理的に契約しようとは思いませんが、対抗する側からすれば過度な競争は体力消耗ものなのは明白、しかも今後の人口減少を考えれば、似たような境遇にある者同士が提携し、手を結ぶことは、戦国時代の大名間の同盟などのいきさつを考えれば、ごく自然なものと考えます。
資本・人事面で手を携えて背面の憂いは除き、今対峙している外敵と真正面でぶつかろうというわけですから、敵対していない両行にとっては渡りに船といったところでしょうか。
まあ、唯一気がかりなのは、肥後銀をモデルとして、その企業体質を晒された小説が数年前に出ていることくらいですが、鹿銀がその真似をしようものなら鹿銀離れになると思われるため、そういうことのないようにしてほしいものです。
さて、そんな鹿銀も、隣は熊本県の肥後銀行(以下肥後銀)と経営統合に向けて協議中という報道を聞き、驚いているところです。
鹿児島の経済圏からして、旧薩摩藩に属する都城市などを抱える宮崎の地方銀行との経営統合の方がすんなり飲み込めるところですが、よりによって熊本県の銀行というところが、今回の裏側を探る上で面白い所です。
まず、鹿銀・肥後銀とも、都市銀行の次の格に当たる地方銀行で、鹿児島・熊本両県の地域一番行といってよい存在です。
そして、両行の主力地域において、他県に本拠を置く銀行からの攻勢を受けています。
鹿児島では宮崎銀行、熊本ではふくおかフィナンシャルグループ傘下の熊本銀行です。
私が住む大隅は宮崎に近いこともあり、時折新聞広告を見るにつけ、宮崎銀行の攻撃的営業姿勢を広告から感じ取っています。
まあ、心理的に契約しようとは思いませんが、対抗する側からすれば過度な競争は体力消耗ものなのは明白、しかも今後の人口減少を考えれば、似たような境遇にある者同士が提携し、手を結ぶことは、戦国時代の大名間の同盟などのいきさつを考えれば、ごく自然なものと考えます。
資本・人事面で手を携えて背面の憂いは除き、今対峙している外敵と真正面でぶつかろうというわけですから、敵対していない両行にとっては渡りに船といったところでしょうか。
まあ、唯一気がかりなのは、肥後銀をモデルとして、その企業体質を晒された小説が数年前に出ていることくらいですが、鹿銀がその真似をしようものなら鹿銀離れになると思われるため、そういうことのないようにしてほしいものです。
2014年02月03日
消費増税を目前にして当座の動きを予測する
自社においても消費増税への対応が決まり、月末にかけてその準備に明け暮れることになりそうですが、今日会社帰りにガソリンを給油しにガソリンスタンドへ赴いたら、いつもより3円ほど値が下がっていました。
これが鹿児島市内だったら167円前後なんだろうなと、11円も安い価格に助かってますが、ふと、給油中に増税したら160円台になるんだろうなと、少し憂鬱になりました。
まあ、揮発油税がガソリン価格に含まれていて、これを除く商品価額自体に消費税がかかる分だったら、3円程度で済むのにと、税に消費税をかける「Tax on Tax」に憤りを感じています。
無論、酒にも酒税に消費税もかかってますから、10%に増税される時には自動車取得税と無縁なバイクに軽自動車税でしわ寄せをかけた代償に、食料品などへの軽減税率も含めて、こうした不公平税制の是正を求めつつ、消費税増税とセットなのが、駆け込み購入です。
今のところは大きな動きは出ていないものの、来月末までの購入については5%で4月以降が8%ですから、年度末にかけて生活必需品については一定程度の駆け込み需要が出てきそうです。
特に、暫定税率騒動の時に客数が大きく変わったのがガソリンで、値上げ前には長い列がスタンドにできたのは記憶に新しいところです。
自社の商材についても言えるのですが、在庫が切れたら増税前に買えるものであっても買えなくなってしまうため、定価で買うもので増税後にまず値下げにならないものについては増税前に買う方が得だと見ます。
不動産や車も駆け込み需要を期待しているように見ますが、過去の経験ではいずれも需要減をカバーするための冷え込み対策で付加価値を付けることもあったことから、様子見でいいと感じます。
4月1日時点で自動車税・軽自動車税も発生しますし、状況によっては増税後の方が結果として得になることもあり得ます。
いろいろな情報が飛び交うでしょうが、ガソリンと長持ちする定価商品は増税前に買った方がよいでしょう。
これが鹿児島市内だったら167円前後なんだろうなと、11円も安い価格に助かってますが、ふと、給油中に増税したら160円台になるんだろうなと、少し憂鬱になりました。
まあ、揮発油税がガソリン価格に含まれていて、これを除く商品価額自体に消費税がかかる分だったら、3円程度で済むのにと、税に消費税をかける「Tax on Tax」に憤りを感じています。
無論、酒にも酒税に消費税もかかってますから、10%に増税される時には自動車取得税と無縁なバイクに軽自動車税でしわ寄せをかけた代償に、食料品などへの軽減税率も含めて、こうした不公平税制の是正を求めつつ、消費税増税とセットなのが、駆け込み購入です。
今のところは大きな動きは出ていないものの、来月末までの購入については5%で4月以降が8%ですから、年度末にかけて生活必需品については一定程度の駆け込み需要が出てきそうです。
特に、暫定税率騒動の時に客数が大きく変わったのがガソリンで、値上げ前には長い列がスタンドにできたのは記憶に新しいところです。
自社の商材についても言えるのですが、在庫が切れたら増税前に買えるものであっても買えなくなってしまうため、定価で買うもので増税後にまず値下げにならないものについては増税前に買う方が得だと見ます。
不動産や車も駆け込み需要を期待しているように見ますが、過去の経験ではいずれも需要減をカバーするための冷え込み対策で付加価値を付けることもあったことから、様子見でいいと感じます。
4月1日時点で自動車税・軽自動車税も発生しますし、状況によっては増税後の方が結果として得になることもあり得ます。
いろいろな情報が飛び交うでしょうが、ガソリンと長持ちする定価商品は増税前に買った方がよいでしょう。
2013年09月10日
軽自動車税増税への動きに考える
消費税増税に伴い、事実上二重課税状態にある自動車取得税(普通車5%【軽乗用車は少し低いが知らないので省略】)を消費税10%時に廃止する方向で動きがあるようですが、と同時に、軽自動車税を倍増させて自動車取得税廃止分の補てんに回そう、という動きもあるようです。
125ccスクーターと250ccバイクを所有する身としては、軽乗用車の方が倍増になる分には何の興味も関心もないものの、二輪車も倍増させる気かと、こちらの方で気をもんでいます。
現状の税金は、125ccが1,600円、250ccが2,400円で、合計すると軽トラックと同額になります。
これが仮に倍増してしまえば8,000円も維持にお金を回さなくてはならず、スクーターを税金がかからない電動自転車に変えるとか、いっそ250ccを手放す(来年春以降高速道路割引料金体系が変わるため)、という行動に移す可能性が出てきます。
現状、税金に加えて5年に1度の自賠責、毎年の任意保険とその分支出を余儀なくされていますので、毎年4,000円の支出増だけなら何とかするも、消費増税分の負担(現状の可処分所得から換算して4~5万円程度)ものしかかり、前述のような選択肢も検討に値してしまう、というわけです。
増税分以上の賃金上昇があれば特に異論を挟むことなく増税やむなしと言えるのですが、これがそのまままかり通れば、窮乏生活へ突入するかどうかまで追い込まれかねません。
財政再建には大賛成ですが、今の私の生活のように、入るを計って出を制す、でないと、どこにしっぺ返しが来るか、為政者の皆様にはよくよく考えてもらわないと、きっと後悔する時が来ます。
私が教員免許を持っていても教員にならないのは転勤生活が嫌ということと、公務員として税金で養われるのが嫌、ということからです。(私学設立を10代の頃に志していたので、その目的に沿って教員免許は取得しました)
国家財政が破たんしたらどうなるか、の地獄絵図は、既に脳裏に浮かんでいます。
ただの増税のつもりであっても、来年度予算の概算要求額の高騰ぶりを目にするに、救いようがないように思えます。
来たるべきXデーに向けて、今日も地道に思うところのことをやっていくのみです。
125ccスクーターと250ccバイクを所有する身としては、軽乗用車の方が倍増になる分には何の興味も関心もないものの、二輪車も倍増させる気かと、こちらの方で気をもんでいます。
現状の税金は、125ccが1,600円、250ccが2,400円で、合計すると軽トラックと同額になります。
これが仮に倍増してしまえば8,000円も維持にお金を回さなくてはならず、スクーターを税金がかからない電動自転車に変えるとか、いっそ250ccを手放す(来年春以降高速道路割引料金体系が変わるため)、という行動に移す可能性が出てきます。
現状、税金に加えて5年に1度の自賠責、毎年の任意保険とその分支出を余儀なくされていますので、毎年4,000円の支出増だけなら何とかするも、消費増税分の負担(現状の可処分所得から換算して4~5万円程度)ものしかかり、前述のような選択肢も検討に値してしまう、というわけです。
増税分以上の賃金上昇があれば特に異論を挟むことなく増税やむなしと言えるのですが、これがそのまままかり通れば、窮乏生活へ突入するかどうかまで追い込まれかねません。
財政再建には大賛成ですが、今の私の生活のように、入るを計って出を制す、でないと、どこにしっぺ返しが来るか、為政者の皆様にはよくよく考えてもらわないと、きっと後悔する時が来ます。
私が教員免許を持っていても教員にならないのは転勤生活が嫌ということと、公務員として税金で養われるのが嫌、ということからです。(私学設立を10代の頃に志していたので、その目的に沿って教員免許は取得しました)
国家財政が破たんしたらどうなるか、の地獄絵図は、既に脳裏に浮かんでいます。
ただの増税のつもりであっても、来年度予算の概算要求額の高騰ぶりを目にするに、救いようがないように思えます。
来たるべきXデーに向けて、今日も地道に思うところのことをやっていくのみです。